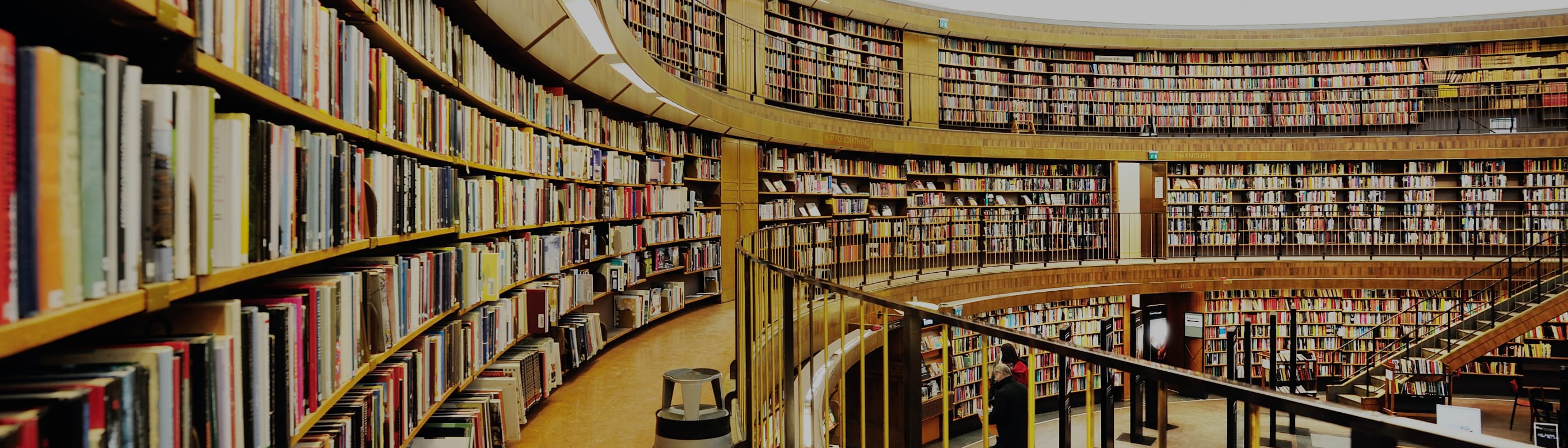見えざる敵が「信頼」を蝕む時代 ― 金融機関の経営者が今、知るべき情報リスクの新常識(第19回)
コラム金融ビジネスの根幹、それは「信頼」です。皆様が日々築き上げてこられた顧客、市場、社会からの信頼は、何物にも代えがたい最も重要な経営資産です。しかし今、その資産が、かつてなく巧妙で目に見えない脅威に晒されています。
2025年9月、日本の情報空間では、政治家に関する過去の動画の切り貼りや、「タンポポの根ががんに効く」といった科学的根拠の乏しい健康情報が拡散していました。これらは金融と無関係に見えるかもしれませんが、社会全体の「信頼」という土壌を静かに蝕む「静かなる侵略」です。
この脅威の本質は、高度なハッキング技術ではありません。人の感情や思い込みを利用し、世論を誘導して社会を混乱させることにあります。攻撃者は、最新技術よりも、人間の心理的な弱点を突く方が効果的だと知っています。これは、貴社のレピュテーション(評判)を毀損する攻撃が、必ずしも高度な技術を必要としないという事実を意味します。たった一つの悪意あるSNS投稿が、瞬く間に取り返しのつかないダメージに発展する可能性があるのです。
この脅威は、2種類の「弾丸」となって金融機関を襲います。
第一の弾丸は、「なりすまし」による直接的な攻撃です。
国勢調査を装う詐欺メールや、著名企業の個人情報漏洩事件が実際に起きています。もし貴社を騙る偽サイトやメールでお客様が被害に遭えば、「あの銀行はセキュリティが甘い」という評判が広まり、信頼の回復は困難を極めます。これはIT部門の問題ではなく、経営の根幹を揺るがすレピュテーションリスクそのものです。
第二の弾丸は、「社会不安」を利用した間接的な攻撃です。
政治や社会へのデマが蔓延し、公的機関への信頼が失われると、経済活動の土台が揺らぎます。「特定の金融機関が反社会的勢力と繋がりがある」といった事実無根のデマを意図的に流された場合、たとえ嘘であっても、ネガティブなイメージの払拭には多大な労力とコストを要します。
ここで専門家として、極めて重要な点を指摘させてください。これら二つの「弾丸」は、決して無関係ではありません。金融犯罪者と、国家が関与するような情報工作の担い手は、実は「公的機関や大企業になりすます」という同じ手口を使います 。サイバー犯罪者が貴社を騙るフィッシングメールを大量に送ることで、お客様は正当な通知メールさえも疑うようになります。つまり、犯罪者の活動が、意図せずして社会全体のデジタル通信への信頼を低下させる「地ならし」を行っているのです。
残念ながら、現在の日本には深刻な弱点が存在します。国際社会ではデジタル化を推進する一方、国内ではいまだにFAXが現役という「デジタル・パラドックス」です。これは、最新鋭のミサイルが飛び交う戦場に、竹槍で臨むようなものです。政府の対策も海外からの大規模攻撃に偏りがちですが、足元ではより身近なデマが社会を蝕んでいます。この脅威認識のズレこそが、日本のアキレス腱です。
では、経営者の皆様はどう立ち向かうべきでしょうか。
- 「うちは大丈夫」という思い込みを捨てる。
情報攻撃のリスクを対岸の火事と捉えず、自社の問題として経営会議の議題に上げてください。 - 守るだけでなく「育てる」発想へ。
問題発生後の「事後対応」には限界があります。従業員や顧客の情報リテラシーを育て、組織全体で「騙されない免疫力」を高める「事前対応」へと戦略を転換すべきです。 - 組織の壁を越えて対話する。
レピュテーションリスクは全社的な課題です。経営層が主導し、部門横断的な危機管理体制を構築することが不可欠です。
「信頼」を築くには歳月がかかりますが、失うのは一瞬です。その一瞬が、デジタル空間で意図的に作り出される時代が来ています。最も重要な資産を守り抜くため、今こそ経営者自らが行動を起こす時です。
※本内容の引用・転載を禁止します。