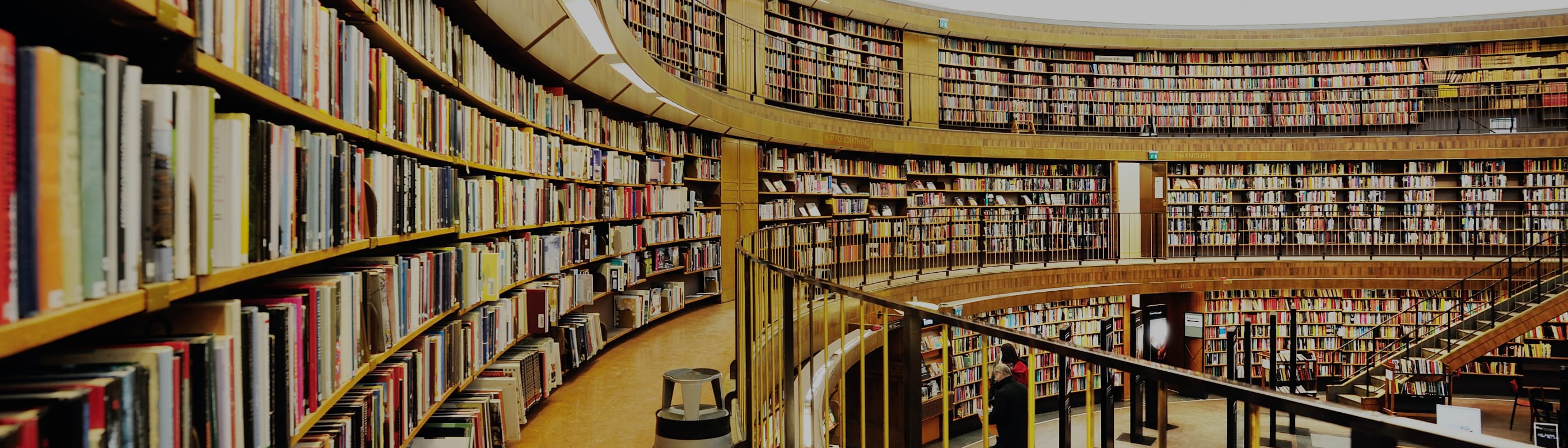【変化への対応力を磨く:自衛隊式マネジメントから学び、図上演習で進む】第7回:統御について(後編)
〜部下を動かす「動機付け」〜
コラム
Jライブラリーをご覧の皆様、こんにちは!
前回は、統御の基盤となるリーダーの理想像についてお話しました。今回は、統御のもう一つの柱である「部下の動機付け」に焦点を当てていきたいと思います。
統御を成功させる上で、リーダーは部下の内面的な「やる気」をいかに引き出すかが問われます。部下のやる気を引き出し、チームとしての一体感を醸成するためには、具体的にどのような要件が関係するのでしょうか。
動機付けの要件として、次の三つが特に重要だと考えられています。
成長の実感、成功体験の積み重ね
新しい業務や困難な課題に直面した際、部下に「自分はできる」という自信を持たせるだけでなく、その前提となる前向きな心構えを育むことです。「どうせ無理だ」と諦めてしまうのか、「まずはやってみよう」と一歩を踏み出せるのかで、成果は大きく変わります。リーダーは、部下が小さな成功体験を重ねられるよう達成可能な目標を設定し、具体的なフィードバックを通じて成長を実感させることが重要です。こうして芽生えた前向きな姿勢が、自信へとつながり、困難な課題にも臆せず挑戦できる力を支えます。
主体性の尊重
「自分の意思で仕事をしている」という感覚を部下に持たせることです。リーダーがすべてを細かく指示するのではなく、ある程度の裁量権を部下に与え、仕事の進め方や優先順位を自分で決めさせることで、部下は「やらされている」という受け身の姿勢から脱却し、「自ら責任をもって取り組む」という主体的な姿勢へと変わります。これにより、部下は仕事に対する当事者意識が高まり、創意工夫が生まれる土壌が育ちます。
チームへの帰属意識(一体感)の醸成
「このチームの一員として貢献したい」という思いを部下に持たせることです。個人がどれだけ優秀であっても、チームとしての一体感がなければ、組織は最大のパフォーマンスを発揮できません。リーダーは、チームの共通の目標やビジョンを繰り返し共有し、日々の業務がチーム全体の成功にどのように繋がっているかを明確にすることで、メンバーの連帯感を深めます。これにより、部下は自分の役割を自覚し、チームの一員であることに喜びや誇りを感じるとともに、「自分ももっと頑張ってみよう」という前向きな気持ちを持てるようになります。
もしこれらの要件が満たされていなかったら、どうなるでしょうか?
メンバーは、「どうせやっても無駄だ」と感じ、自己成長への意欲を失うかもしれません。「やらされている仕事」にやりがいを見出せず、責任感も希薄になるかもしれません。「自分だけ頑張っても意味がない」と孤立感を深め、チームの団結は崩壊するかもしれません。
これらの状態は、チーム全体の活力を奪い、統御を失わせる深刻な事態を招きます。リーダーは、これらの要件を満たすことが、部下の潜在能力を引き出し、最強のチームを築くための第一歩であると肝に銘じる必要があります。
自衛隊とITベンチャー企業が示す、リーダーシップの多様性
動機付けの手法は、組織の文化やメンバーの特性によって大きく異なります。対照的な二つの組織は、動機付けの多様性の参考になります。
-自衛隊のケース
自衛隊では、「公のために任務を全うする」という強い目的意識が、隊員の行動原理となっています。規律や訓練を通じて組織への帰属意識を高め、チーム一丸となって任務を遂行します。ここでは、個人の自己決定感よりも、組織全体の規律と目標達成が重視される傾向にあります。よって、メンバーはチームとの一体感や帰属意識は感じやすい環境におかれますが、個々の主体性は感じにくくなり、自己の成長をチームに求めにくいと感じるようになります。
このような環境では、リーダーはメンバー個別に成果や成長をフォローアップすることが大切です。これにより、メンバーは自己の成長とチームの目標達成とを重ねることが可能となります。
-ITベンチャー企業のケース
一方、ITベンチャー企業では、社員一人ひとりのアイデアや創造性が組織の成長に直結します。このため、裁量権を大きく与え、自己決定感を尊重するマネジメントが一般的です。リーダーは、メンバーの挑戦を支援し、失敗を恐れずに新しいアイデアを試せる環境を整えることが重要になります。ここでは、個人の自己決定感が、組織の成長を加速させる原動力となるため、メンバーは自己の成長や主体性を感じやすくなります。一方、企業は市場の動向に能動的に対応するため、チーム目標が変化しやすく、必要に応じチーム編成も流動的になります。チームの一体感や帰属意識は希薄となりやすい環境となります。
このような環境では、リーダーは、チームミーティングなどを通じたチームビルディングを重要視する必要があります。
あなたのチームに必要なのは、どの「動機付け」ですか?
この二つの事例から、統御の手法が組織の目的や文化によって異なることがわかります。あなたのチームは、どちらの組織の特性に近いでしょうか?
例えば、厳格な品質管理が求められる製造業や金融業では、自衛隊のように明確なルールと規律、チームの一体感を重視する環境の中で、個々の成長をフォローアップしていく統御が有効かもしれません。
一方、クリエイティブな発想やスピーディな意思決定が求められるマーケティングや開発部門では、ITベンチャー企業のように個人の裁量権を尊重し、自己決定感を高めつつ、チームの一体感を感じさせる施策を取り入れるなどの統御が適しているでしょう。
リーダーは、画一的な動機付けを行うのではなく、チームの特性やメンバーの成熟度に合わせて、柔軟に統御の手法を使い分ける必要があります。
これらの使い分けを意識することで、リーダーはメンバーの潜在能力を最大限に引き出し、最強のチームを作り上げることができるでしょう。
まとめ
統御を成功させる鍵は、リーダーがメンバーを「動かす」のではなく、メンバー自身が「動きたくなる」ような環境を創り出すことです。そして、その環境づくりには、「成長の実感」「主体性」「チームへの帰属意識」という三つの要件が不可欠です。
ぜひ、皆様も自らのチームに合った動機付けの手法を見つけ出し、メンバーの潜在能力を最大限に引き出してください。
※本内容の引用・転載を禁止します。