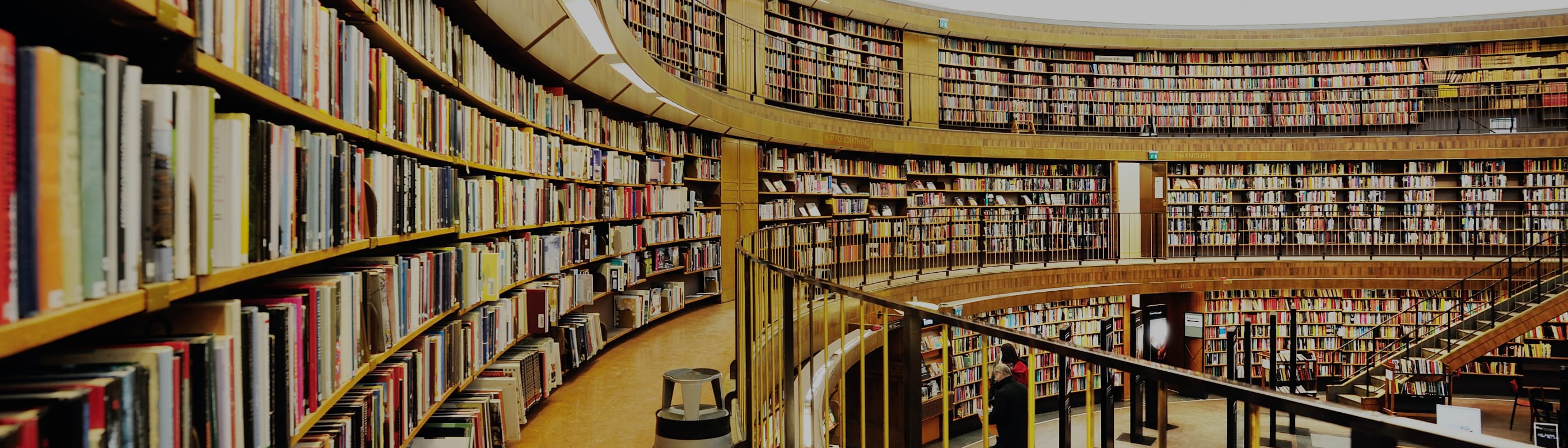〔変化をチャンスに 〜 変化を捉える視点と思考 〜〕
第69回:開発と運用の新しいカタチ(3)
コラム
<はじめに>
「オープンソース」という言葉を聞いたことがあるだろうか。
コンピュータプログラムの著作権の一部を放棄し、誰でもソースコードを入手・利用できるソフトウェア開発モデルのことをいう。また、このようなモデルで開発されるソフトウェアをOSS (Open Source Software) という。
(*) https://ja.wikipedia.org/wiki/オープンソース
(*) ちなみに、オープンソースハードウェアという考え方も存在する。
オープンソースの歴史は長い。考え方そのものは古くからあった。言葉としての「オープンソース」が市民権を得たのは1998年頃。実は筆者も多数のOSSに携わっていたので、当時の議論を憶えている。
(*) ftpmirror、bomb、radix、dripcast、などは筆者作のOSS (笑)
え? プログラムのソースコードを公開するって? 何の意味が? もったいない…
と思うだろうか。
オープンソースはプログラムの普及を促す。また、多くの人が機能追加、改修・改善に携わることで積極的なコラボレーションが可能になる。Linux、Java、Android、Firefox、他にも身近にオープンソースで開発されるソフトウェアは多数ある。前々回 (第67回) 紹介した git (ギット) もオープンソースで開発されている。
オープンソースがイノベーションに貢献する事例は多い。今回は、DevOpsが急速に広がった背景で、実はオープンソースの開発モデルが大活躍した、という事例を紹介してみよう。
本稿は前々回 (第67回)、前回 (第68回) の続編である。今回もDevOps (デブオプス) を切り口に議論する。今回はDevOpsのための分散型の開発環境を提供するGitLabの取り組みと、その挑戦について考察する。
<GitLabの概要と歴史>
GitLab社 (GitLab Inc.) はDevOpsのための分散型開発環境をオールインワン (All-in-1) で提供する。サブスクリプション型でネットワーク経由で開発環境を利用する SaaS (Software as a Service) モデルを主とする。Thales Group (第67回で紹介) や Sigma Defense (第68回で紹介) がDevOps環境として採用しているのがGitLab社のサービスである。同社のサービスを利用する企業は多い。
(*) https://about.gitlab.com/ja-jp/platform/
https://about.gitlab.com/ja-jp/customers/
同社の起源は2011年10月に遡る。DevOpsを実践する開発・運用環境を実現するためのソフトウェア (ソフトウェアの名称も GitLab) の開発が始まった。DevOpsの議論がスタートしたばかりのころ、Dmitry Zaporozhets氏がたった1人で開始したオープンソースプロジェクトだった。
同氏はウクライナで水道も引かれていない家に暮らしていたらしい。曰く「毎日の井戸への水汲みよりもソフトウェア開発者たちがコラボレーションする良いツールがないことのほうが大きな問題だと感じていた」ことがGitLabプロジェクト開始のきっかけとか。
(*) https://coralcap.co/2021/10/gitlab-ipo/
GitLabの躍進には驚愕する。最初は先行するGitHubの「丸パクリ」とも言われたが、やがて多数の開発者がプロジェクトに参加し、また、多数の企業で導入が進んだ。2014年に法人化し、2015年には、かの有名なシードアクセラレーター (ベンチャー支援組織) である “Y Combinator” に参加した。2021年にはNASDAQに上場、時価総額110億ドル (約1.6兆円) にも達した (2025年現在の時価総額は66.8億ドル)。
ひゃー (驚)
<GitLab now>
GitLab社の最新状況についても簡単に触れておこう。2025年現在の同社のビジネスの根幹は、GitLabというコンピュータプログラムを売ることではなく、GitLabが使える開発・運用基盤を利用してもらうことである。導入企業数は未公開だが、登録ユーザーは5,000万人とも言われる。
同社は自らDevOpsを実践していることを強くアピールしている。GitLabのプログラムそのものは今もオープンソースであり4,600人が開発に携わっている。
(*) GitLabのオープンソースライセンスはコミュニティ向け、企業向けの2種類ある。
システムとしてのGitLabの継続的な開発・改修・導入も繰り返している。2025年8月現在、166ヶ月連続でシステムを更新しているという (記録も更新中、笑)。これだけ巨大なプラットフォームシステムがDevOpsで開発・運用できることをGitLab社が自ら証明しているのは注目に値する。
加えて、GitLabに関連して強調したいことがある。同社の社員は現在2,300名、世界60ヶ国で働いている。一方、同社のオフィス数は “0” である。
オフィスが「ゼロ」ってどういうことだろう。そういえば、Thales GroupやSigma Defenseの事例でも、分散型の開発・運用基盤を構築することで拠点に依存しない組織づくりが可能になったという話があった。
実は、同社がオフィスを持たないことは明確な信念に基づいている。このあたりは、次回、さらに深堀りして紹介・考察したい。
<変化の視点>
開発モデルにも「変化」が進んでいた。オープンソースの開発モデルはその一つである。当時、日本企業 (特に大企業) には「商用プログラムのソースコードの公開はあり得ない」と考える風潮があった。一方、海外では、オープンソースで市場を席巻するような新しい仕組みがいくつも登場していたことはよく覚えている。(筆者もオープンソースプロジェクトに関わっていて、実は当事者だった、笑)。
GitLabの成功を考察する際、その開発モデルは注目に値する。オープンソースプロジェクトは多数の開発者とのコラボレーションを促し、同時に、新たな仕組みを社会に浸透させることを容易にする。特にイノベーティブな仕組みを普及させるときには、オープンソース戦略は有効なのだろう。GitLabの躍進は参考にしたい。
開発モデルの変化は新たなビジネスモデルの登場にも寄与した。GitLabはコンピュータープログラムを販売するのではなく、DevOpsの開発・運用環境を使ってもらうことをサービス化した。GitLabの仕組みそのものが機能追加・改修・改善を頻繁に繰り返すことを宿命としており、それをビジネス化したとも言える。
<終わりに>
今回は開発モデルの変化、特にオープンソースの開発モデルに注目して、それがどんなイノベーションを生み出したのかを考察した。GitLabの事例は、それが単にソースコードを公開する・しない、の話ではない。新しい仕組みを社会に迅速に普及させ、多数の開発者とのコラボレーションが促されることにより大きな変革を起こすために、オープンソースの開発モデルが戦略の選択肢になる、ことを教えてくれた。
DevOpsとオープンソースの関係についても触れておきたい。DevOpsが急速に広がった背景にはオープンソースの開発モデルがあった。バージョン管理システムのgitも、コラボレーション型の開発プラットフォームであるgithubも、さらには、本稿で紹介したDevOpsプラットフォームのGitLabも、すべてオープンソースである。コラボレーションを前提とする文化はDevOpsと相性が良かったのかもしれない。
社会は急速に変わりつつある。今、我々が直面しているイノベーションの背景にどんな「変化」があるのか。また、その「変化」がどんなインパクトをもたらすのか。変化を捉える視点と思考がますます重要になりそうだ。
※本内容の引用・転載を禁止します。